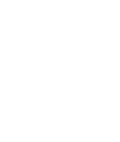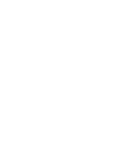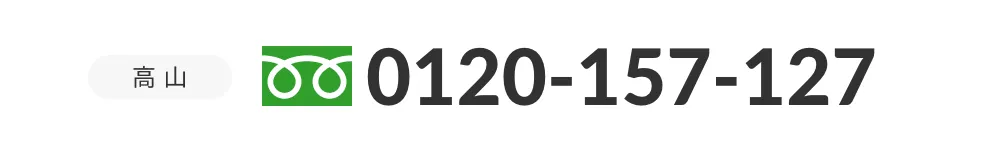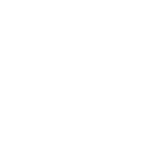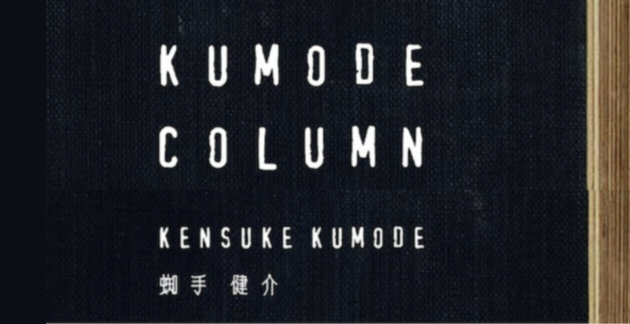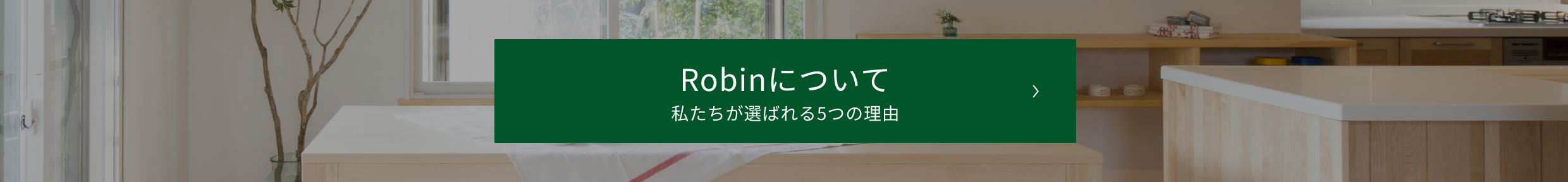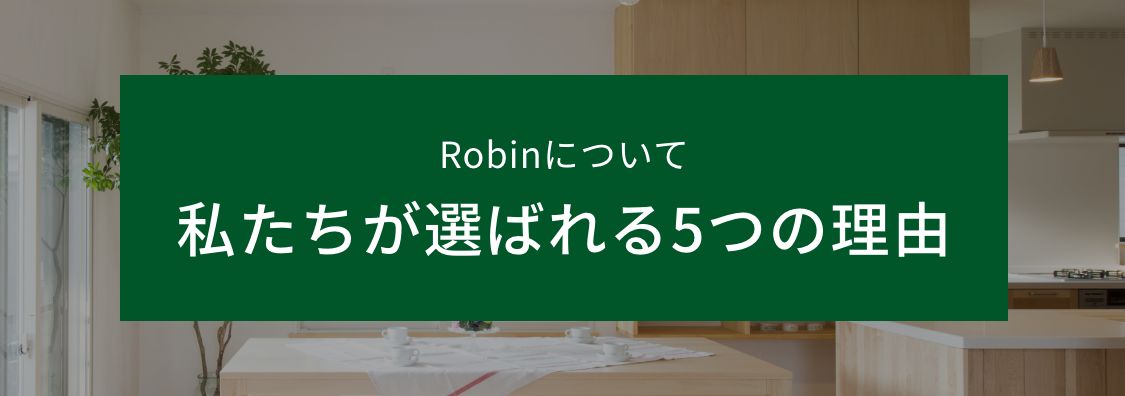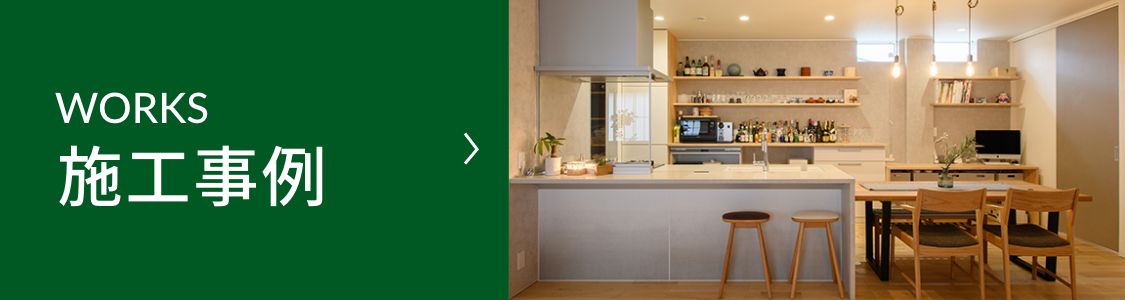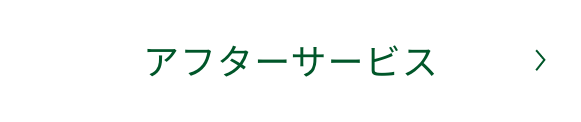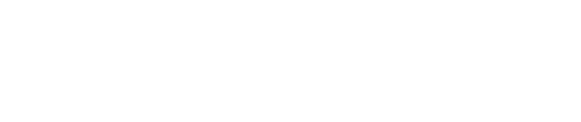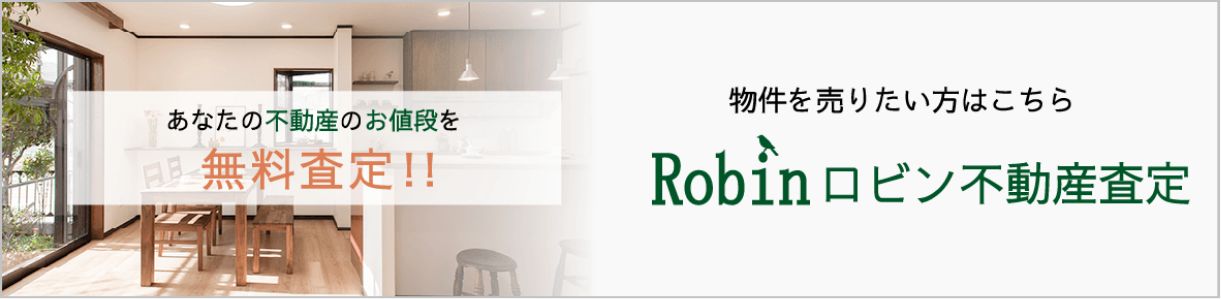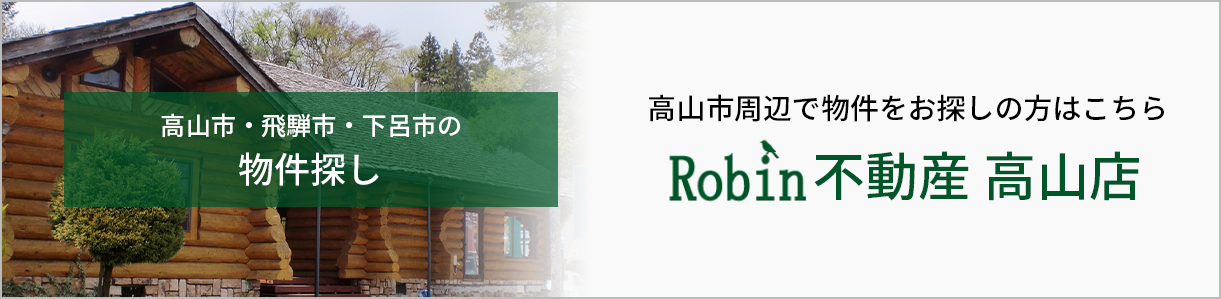(5)こどもの日に思う。自分で考え生きるということ(2025.5.5)
最近、NHKが報じたニュースが印象に残っている。
「訪問介護が人手不足で、サービスの依頼を断る事業所が急増している」というものだった。
訪問介護 人出不足で依頼断る事業所相次ぐ 労働組合調査(NHK 2025年5月5日)
介護サービスは、必要なときに誰もが等しく受けられる――そんな前提で制度設計されてきたはずだ。
だが現実には、その“平等性”がすでに崩れつつある。団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となり、介護需要はこれからピークを迎える。
この世代を支えるには、莫大な労働力と財源が必要だ。だが、その担い手であるはずの現役世代は減る一方。制度が成り立つはずがない。
介護報酬を引き上げれば人が集まる――そうした意見もあるが、それはすでに時代遅れだ。他業界も同様に人材不足にあえぎ、待遇改善を図っている以上、介護業界だけが特別に人を集めることは難しい。構造的な人材不足という問題に、待遇だけで太刀打ちすることはできない。
では、外国人労働者で補うという選択肢はどうか。しかし、日本の受け入れ制度は複雑で制限も多く、現場では単なる「穴埋め要員」として扱われがちだ。低賃金でキャリアパスも描けない環境に、長期的に優秀な人材が集まるはずがない。
結論として、国が長年掲げてきた「介護は誰にでも安心して受けられる社会」という政策は、構造的に破綻しかかっている。そしてそれは、介護に限った話ではない。
先日、馴染みの焼肉屋で、隣の席に座っていた三世代家族の会話が聞こえてきた。
30代前後の息子世代の男性が、「最近、給与が下がってさ」とこぼすと、奥さんは「出費を我慢しないとね」と答えていた。祖父母は「大変だねえ」とうなずきながら、「孫にはちゃんと教育を受けさせないと」とも語っていた。
「何かアルバイトでもしようかな」と、息子がぽつりとつぶやく。
収入が減ったのなら、働く時間を増やすという発想は自然だ。副業やバイトという手段もあるだろう。だが、本来は“本業”で成果を伸ばし、報酬を増やすことが最も健全かつ持続的なやり方だ。
そこで彼の言葉が耳に残った。「でも、会社も残業も休日出勤もさせてくれないし」
そう、働きたくても働けないのだ。
理由は明確だ。国が推し進めた「働き方改革」である。企業は労働時間を厳格に管理し、違反すれば刑事罰の対象となる。だからこそ会社も、法令遵守の観点から“働かせない”という判断をせざるを得ない。
つまり、働きたいのに働けない。それは会社の判断というより、制度によって縛られている結果なのだ。そしてその制度を作ってきたのは、他でもない「国」である。
私は「もっと働きたい」と思うのは自然なことであり、健全な感覚だと考えている。だが今の日本では、その感覚がどこかズレたもののように扱われる空気すらある。
国はここ数年、「もっと休もう」「人生を楽しもう」「自分の時間を大切に」と繰り返し言ってきた。
もちろん、それ自体は間違いではない。だが結果として、「仕事は人生を犠牲にするものだから、なるべく減らすべきだ」というメッセージとして受け止められていないだろうか。
今を楽しむことにばかり重きが置かれ、努力・労働・成長といった概念がどこか古臭く、悪のように語られていないか。“消費型の生き方”だけが正解であるかのような風潮に、私は違和感を覚える。
介護の問題にせよ、働き方の問題にせよ、共通して見えるのは、国の制度には限界があるという現実だ。
「誰もが等しく受けられるサービス」も、「制度に従っていれば報われる人生」も、もはや幻想だ。それなのに、いまだに「国がなんとかしてくれる」という期待を捨てられない人が多い。
だが、国の多くの制度は昭和初期に設計されたものが土台になっている。経済が右肩上がりで、人口が増え続けることを前提にしたモデルだ。いま、その前提は完全に崩れた。経済は縮小し、人口は減り、国力は相対的に低下しつつある。
国内の方向性すら、米国大統領の一声で左右される。もはや「誰かが整えてくれる」時代ではない。国家は制度を提供するが、その使い方と結果の責任は個人に委ねられている。ならば、私たちは自らの意志で「どう生きるか」を選ばなければならない。
それが、少子高齢化・人口減少時代の日本において、最も現実的で強い“ライフハック”なのだと思う。

最高経営責任者 蜘手 健介
ロビンのリフォーム・リノベーション一覧
ロビンは、換気扇レンジフードの交換リフォームから、設計士がご提案するフルリノベーション、注文住宅まで幅広く対応しております。
それぞれのサービスの紹介、施工事例、お客様の声などをご覧ください。