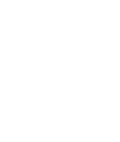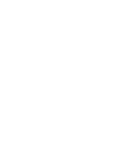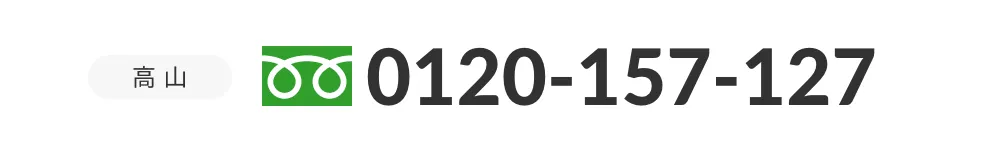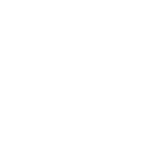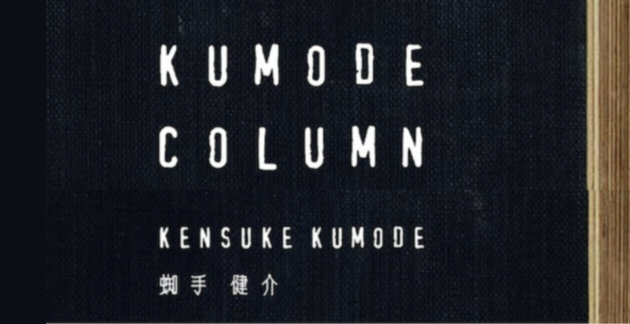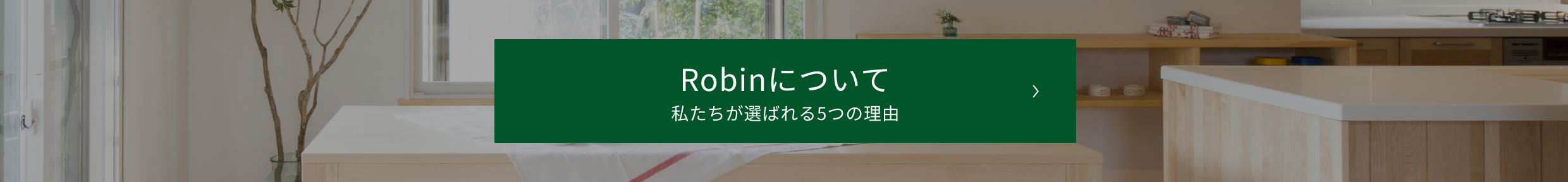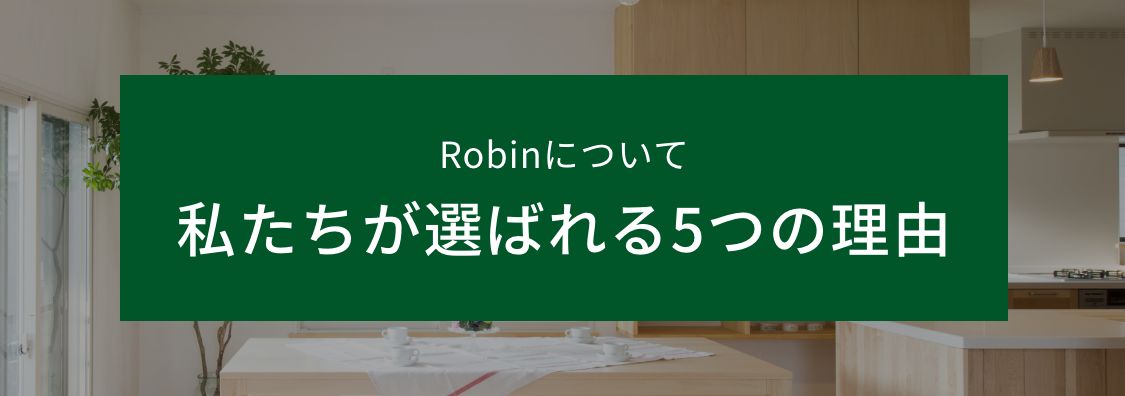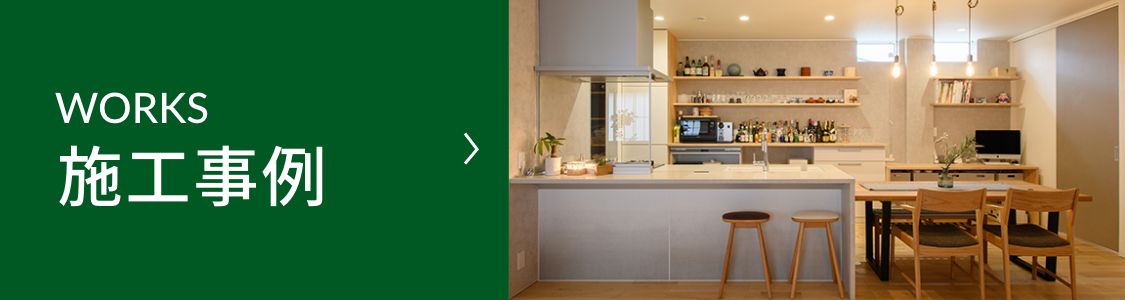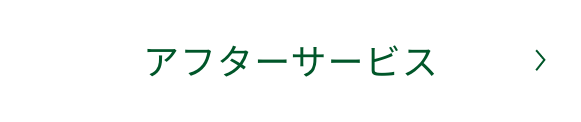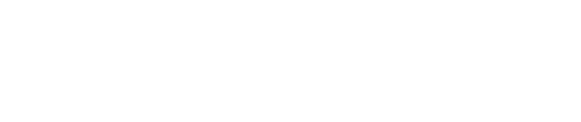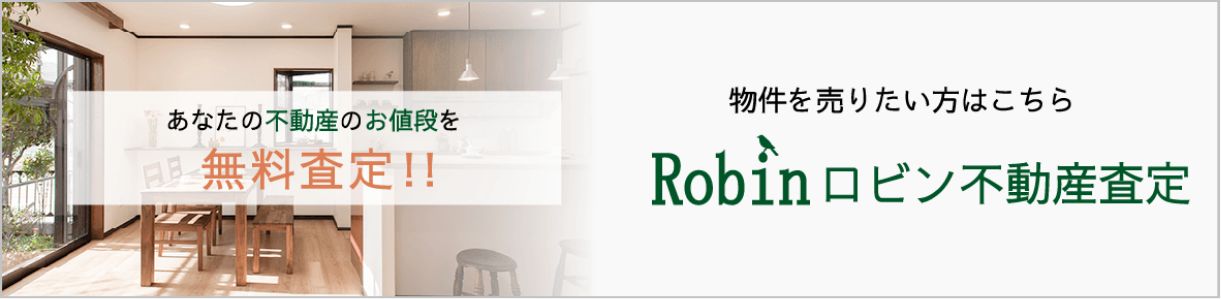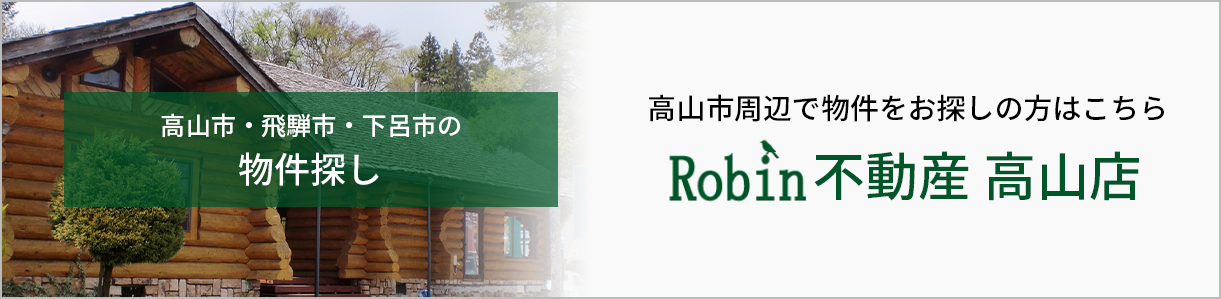(30)経営の土台に問われる「倫理」と「持続性」(2025.10.28)
私が通っていたジムが一昨年、破産し事業は社員の方へ引き継がれたのだが、その方によると前オーナーがコロナ助成金を不正受給していたことが発覚したという。破産してから判明したのか、不正受給が判明してから破産したのかは定かではないが、気になって不正受給について調べてみると処罰された企業・商店の多くは倒産、廃業、破産などに至っているケースが多く驚いた。
「不正受給しておいて倒産するなんて」と感じた次第。
コロナ禍という未曾有の危機の中、政府は中小企業や個人事業主を救うべく、持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金といった緊急支援策を矢継ぎ早に打ち出した。制度設計にはスピードと柔軟性が求められ、審査は簡略化された。多くの企業がその恩恵を受け、危機を乗り越える力とした一方で、それを悪用し、不正受給に走った事業者も少なくなかった。
近年、こうした不正受給を行った企業・商店が次々と倒産・廃業に至っている。その多くは「制度をうまく使っただけ」「誰でもやっている」といった意識のまま資金を得て、一時的に経営を繋いだが、制度が終了し、経営実態に向き合わざるを得なくなった瞬間、資金繰りが尽き、社会的信用も失って崩壊した。
この一連の流れから、私たち経営者が学ぶべきことは何だろうか。
第一に、経営の根幹に「倫理」と「信頼」があるという当たり前の原則だ。事業は社会との関係性の中で成り立つ。顧客、取引先、金融機関、従業員、地域社会…。そのすべてとの信頼関係の上に企業の継続性がある。不正受給は一時的に資金を手にする手段かもしれないが、同時にその信頼の基盤を壊す行為でもある。制度は「困っている事業者を救う」ためのものであり、それを自らに都合よく解釈して不正を働くということは、社会と制度への裏切りであり、長期的に見れば企業価値を大きく毀損する。
第二に、「持続可能な経営」の本質に立ち返る必要があるということだ。危機時には資金繰りが最優先になる。しかし、危機を乗り越えるとは、単に数ヶ月を生き延びることではない。本当の危機対応とは、収益構造を見直し、事業ポートフォリオを整理し、将来に向けて企業を再構築していくことだ。不正受給に依存する経営は、砂上の楼閣のようなものであり、いずれは崩れる運命にある。
第三に、制度を活用することと、制度に依存することは違うという視点だ。真っ当に制度を使った企業の多くは、その後も本業の立て直しや事業転換に取り組み、持ち直している。一方で、制度そのものを「金のなる木」のように扱い、あてにしたまま事業の改革に手を付けなかった企業は、制度終了と同時に自滅している。補助金や助成金はあくまで「一時的な応急処置」であり、「治療」ではない。制度活用後の自立こそが重要なのだ。
経営者は常に「選択」を迫られる。苦しいときに、倫理を貫くか、目先の利益に走るか。その選択の積み重ねが、企業文化となり、社員の意識となり、顧客の信頼となって返ってくる。今回のコロナ不正受給の事例は、制度の穴や監督の緩さを批判するよりも、「倫理を欠いた経営」がいかに脆く、持続しないかを示す生きた教材である。
企業の存在意義は、社会に価値を提供し、信頼を得ながら持続的に成長することにある。どれだけ困難な状況でも、正道を歩む経営者こそが、最終的に社員・顧客・社会から支持され、企業を未来へ導くことができる。
今後もさまざまな支援制度や助成金が登場するだろう。その時、我々は「使っていい制度か」だけでなく、「使うべきか」「使った後にどうするか」を問える経営者でありたい。制度と真摯に向き合い、信頼される経営を積み重ねていくことこそが、これからの時代における企業の“生存戦略”ではないだろうか。

最高経営責任者 蜘手 健介
ロビンのリフォーム・リノベーション一覧
ロビンは、換気扇レンジフードの交換リフォームから、設計士がご提案するフルリノベーション、注文住宅まで幅広く対応しております。
それぞれのサービスの紹介、施工事例、お客様の声などをご覧ください。