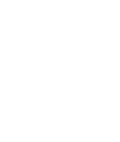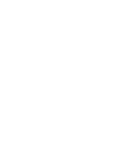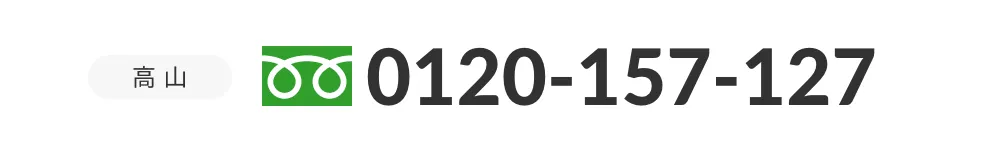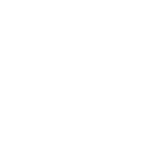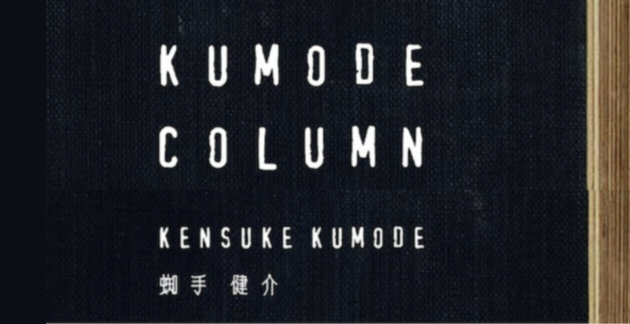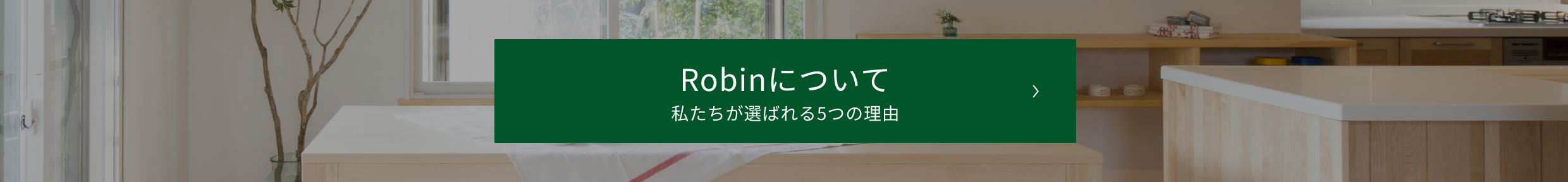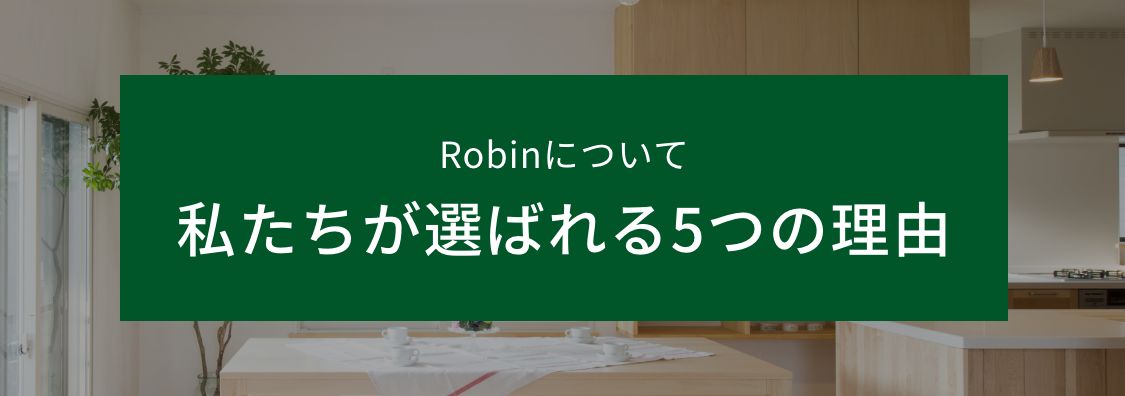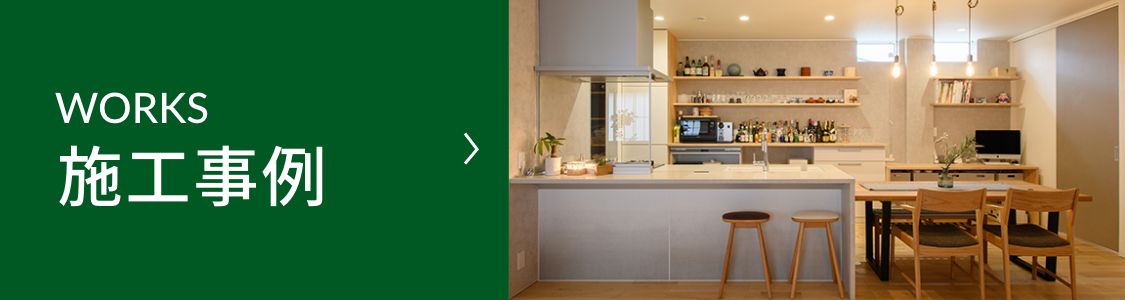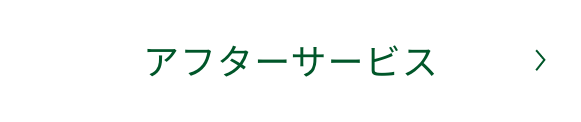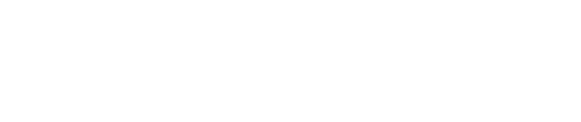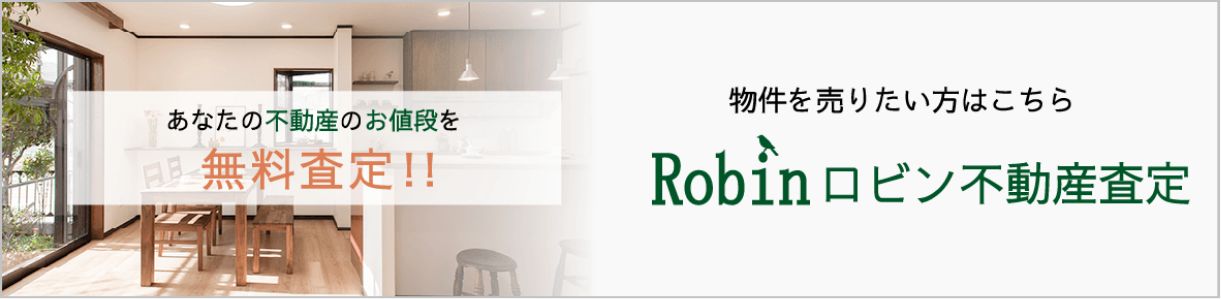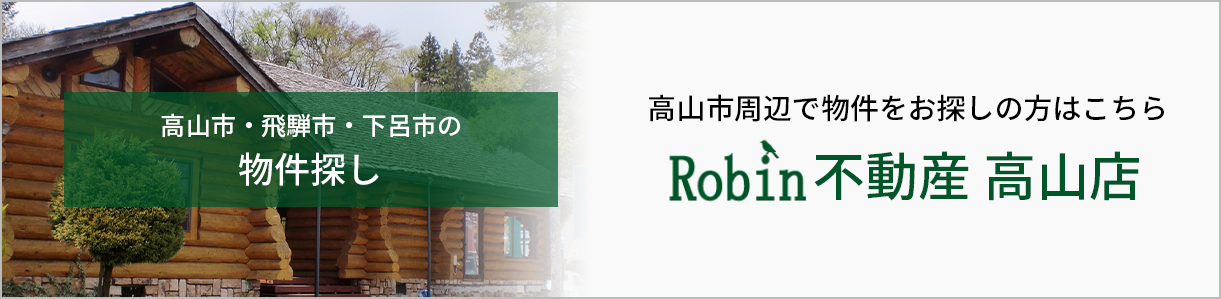(27)座学の重要性
子どもの頃、社会科で「軍事産業」について学んだ時、なんて卑劣で汚い商売なんだと思った。戦争で人が死に、その裏で企業が利益を得る。そんな構図を、子どもながらに強く嫌悪した記憶がある。
だが、大人になって世界を見ると、現実はもっと複雑である。
現在、金(ゴールド)は史上最高値を更新し、終わらないロシア・ウクライナ紛争を背景に、欧州の軍事関連株は右肩上がりを続けている。
もしあなたが投資家だとして利益を得ているとしよう
「株価やゴールドが上がり続けているのは戦争が続いているからだとすると、あなたは戦争に反対するか、それとも資産価値の上昇を望むか」と尋ねたら、どんな答えが返ってくるだろう。
社会とは、なんと残酷で、矛盾に満ちた構造なのだろうか。子どもの頃に聞いた“軍事産業”の話が、いまになってようやく腑に落ちた気がした。
閑話休題。
社員教育、そして社会教育において必要なものは、「座学―実践―フィードバック」である。特に社会に出ると、座学は軽視されやすく「現場で覚えろ」「実践こそが教育だ」と言われる。
しかし、実践教育だけでは初速は速くとも、やがて伸び悩む。なぜなら、座学によって知識が体系化されていないために、自分の経験を整理できず、再現性を持たないからである。
座学があるからこそ、実践の中で「腑に落ちる」瞬間が生まれる。この体験が、人を次の段階へと押し上げる力になる。
たとえば自動車免許の取得を考えてみる。もし座学(学科)がなく、実践だけで免許を与えたらどうなるか。交通法規を知らず、標識の意味も理解しないまま走れば、事故は必然である。運転技術がどれほど上達しても、理論がなければ安全は守れない。これはあらゆる教育に共通する構造である。
ゴルフの上達もよく似ている。スイング理論やボールフライトの法則を理解して練習する人は、修正点を明確に捉え、短期間で上達する。逆に「とにかく打てばうまくなる」と信じる人は、努力量に見合う成果を得られない。上手な人の話を聞いても理解できないのは、基礎理論という座学が欠けているからだ。「なぜその動きが必要か」を理解している人だけが、経験を技術に変えられる。
調理の世界でも同じである。レシピを覚えるだけでは応用が利かない。座学で「なぜ塩を最初に入れるのか」「なぜ火加減が味を変えるのか」を学ぶからこそ、食材や分量が変わっても同じ味を再現できる。座学とは「決まりごと」ではなく、「再現性を生むための思考の道具」なのである。
営業教育でも同じだ。座学がある場合、営業プロセスや心理学、顧客タイプ別対応法を理解してから商談に臨む。すると、なぜ売れたのか、なぜ売れなかったのかを分析できる。一方、座学がない場合は、上司の真似をして現場に出る。結果は感覚頼みとなり、個人差が大きく、再現性が失われる。経験を重ねても「なぜうまくいったのか」がわからないまま、伸び悩んでいく。
そして会社経営も例外ではない。経営理論や会計の基礎を学んでいる経営者は、数字で判断し、組織を育てる。一方、経験と勘だけで経営していると、短期的な成功に左右され、やがて属人化や不正の温床となる。ドラッカーを読んだ経営者は「顧客とは誰か?」を問うが、読まない経営者は「とにかく売れればいい」に陥る。理論を知っているからこそ、経験に意味を与えられるのだ。
座学がある教育は、経験を意味づける。座学がない教育は、経験を散らかす。前者は成長し、後者は停滞する。実践は確かに大切だが、実践とは理論を試す場であり、座学の延長線上にある。座学がなければ、実践は「偶然の成功と失敗の繰り返し」にすぎない。フィードバックが加わって初めて、経験が知に昇華し、成長のサイクルが回り始める。
AI時代のいま、座学の価値はむしろ高まっている。AIは質問に答えることは得意だが、「体系だった理解」を教えることはできない。座学とは、AIに答えを聞くことではなく、原理・構造・背景を理解することにある。つまり、AI時代にこそ人間が取り戻すべきは、“座して学ぶ力”である。座学とは、知識を増やすためではなく、経験を意味づけ、人生を設計するための礎だと思う。
座学を軽視するなかれ、座学の機会を損じるなかれ、である。

最高経営責任者 蜘手 健介
ロビンのリフォーム・リノベーション一覧
ロビンは、換気扇レンジフードの交換リフォームから、設計士がご提案するフルリノベーション、注文住宅まで幅広く対応しております。
それぞれのサービスの紹介、施工事例、お客様の声などをご覧ください。