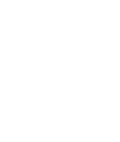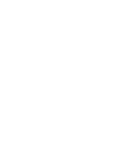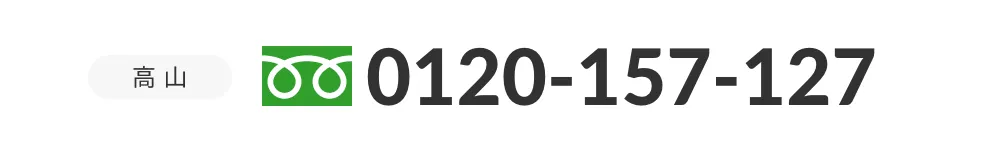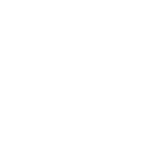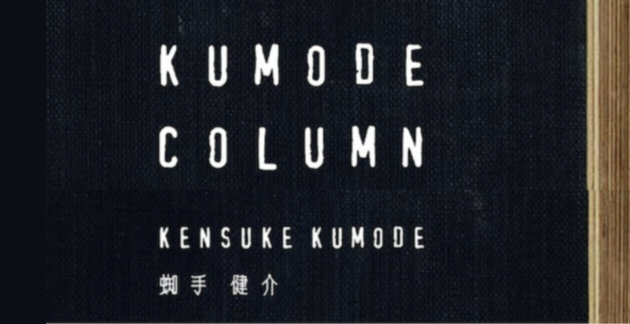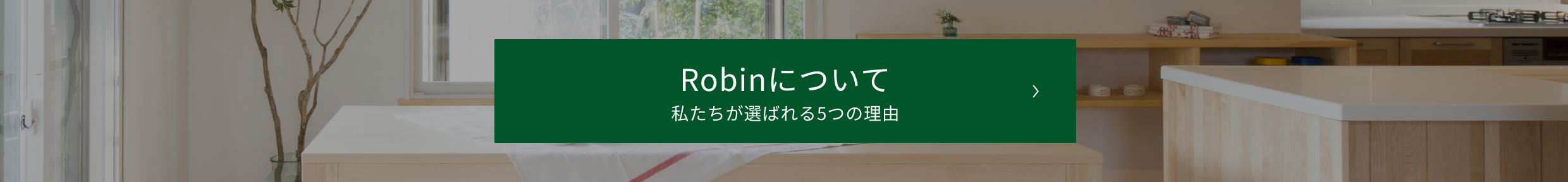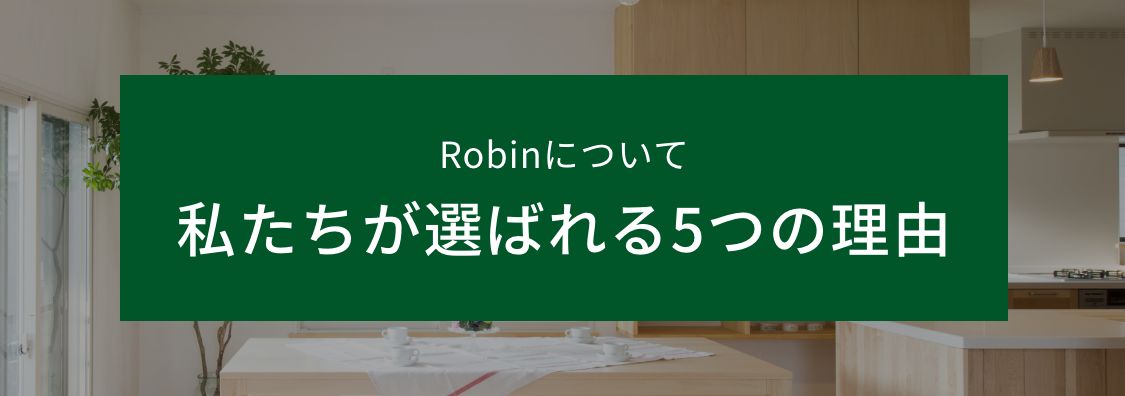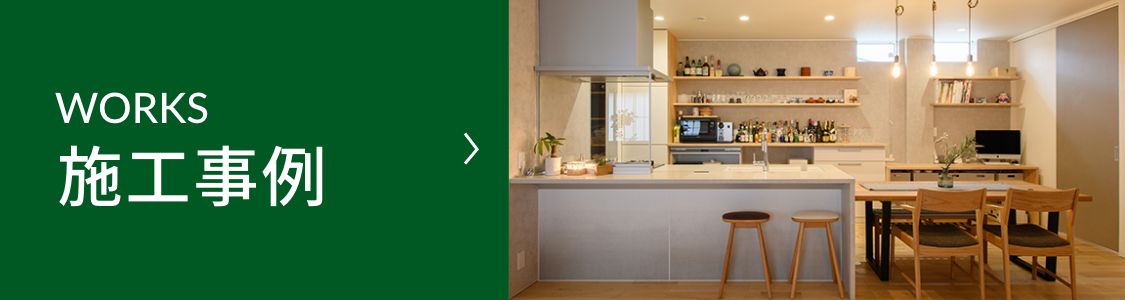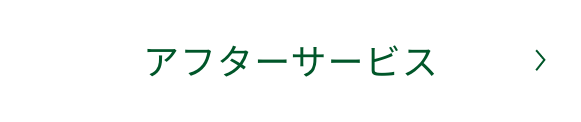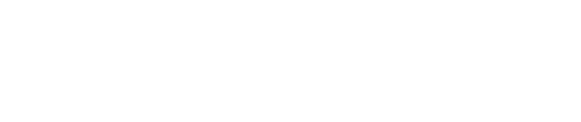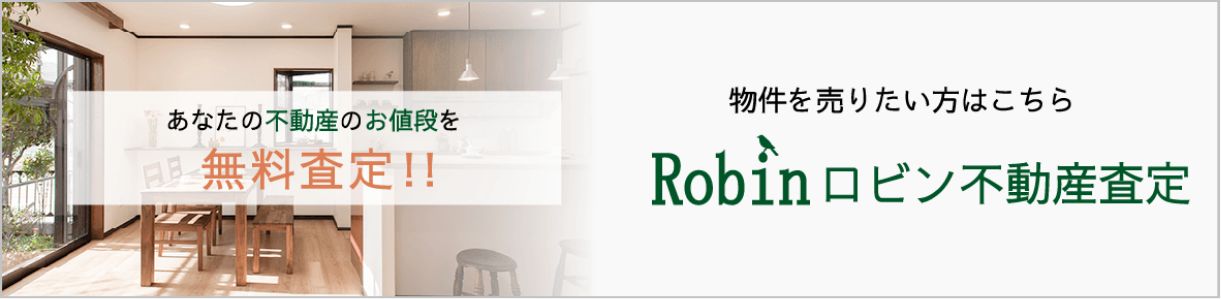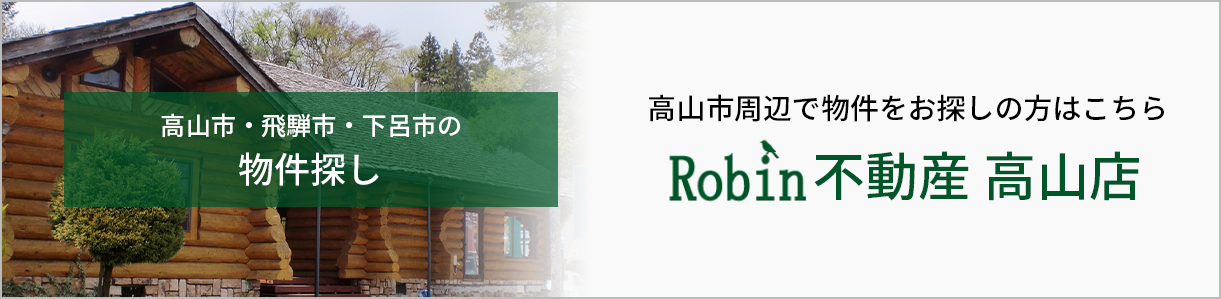(30)「人間の手」と「ノンファイヤー人生」(2025.11.3)
日経有料版に興味深いコラムがあったのでご紹介する。
米国で「ブルーカラービリオネア」現象 A I発展で潤う肉体労働者
(日経2025年11月2日)
米国で「ブルーカラービリオネア」と呼ばれる現象が注目されている。AI(人工知能)の進化により、弁護士やプログラマーなどホワイトカラーの職業が効率化される一方、AIに代替できない技能職の価値が急上昇している。米マンハッタンでは、音響装置の修理技師がポルシェで現れ、数千ドルの請求をするという光景も珍しくない。かつて時給700〜1000ドルを誇った弁護士が、AIの導入で報酬単価を下げる一方、配管工や空調整備士の年収が医師を上回る事例も出てきた。
AIには、現場での判断や人との信頼関係、感覚的な手仕事を再現することはできない。そのため、配管工・溶接工・空調整備士といった技能職の需要が拡大し、米国では「エレベーター技師」の年収中央値が約10万6,000ドル(約1,600万円)に達している。職業訓練校の入学者は前年比20%増であり、年間授業料9,000ドルという低コストで即戦力が育つ。企業は卒業生の採用に積極的で、政府も職業訓練支援を拡充している。AIによる知識労働の代替が進む一方、「人間の手」で働く仕事が社会に不可欠な存在として再評価されているのである。
米フォード・モーターのファーリーCEOも「AIはホワイトカラーの半分を置き換える」と警鐘を鳴らし、技能職を“エッセンシャルワーカー”と位置づけた。建設業界では2026年までに約50万人の新規労働者が必要とされ、職人が再び主役となる時代が訪れている。
こうしてアメリカでは、「高学歴=高収入」という従来の常識が崩れ始め、知識よりも経験、理論よりも現場、頭脳よりも手が価値を生む社会構造へと移行しつつある。(ここまで要約)
アメリカの状況は象徴的だ。AIによって弁護士やプログラマーの仕事は効率化され、報酬は下落した。かつて高収入の代名詞だったホワイトカラーが、AIリサーチや自動コード生成に置き換えられつつある。一方、配管工や空調整備士など、現場で手と身体を使って働く人々の収入は急上昇している。AIには、現場での判断力、柔軟な対応、そして「人間同士の信頼関係」を築く力がない。ここにこそ、人間の手の価値が宿る。
私たちもまた、AIの影響を肌で感じている。
ショート動画制作の単価は、わずか数年で桁が一つ下がった。AIによる自動編集が普及し、人の手による制作との差が見えにくくなった。SaaSやアプリ開発も格安化が進み、スピードと柔軟性が圧倒的に向上している。中小企業にとっては恩恵もあるが、同時に市場価格の崩壊を招いていることも事実だ。AIがもたらす「単価の下落」は、雇用と市場全体に確実なインパクトを与えている。
その流れの先に、アメリカの「ブルーカラービリオネア」がある。
AIでは代替できない「人の手」が、むしろ新しい富の源泉になっているのだ。
日本ではこの現象がまだ顕在化していないが、特に利益が出にくいとされる住宅リフォーム業界にこそ大きなヒントがある。リフォームは、人の暮らしに深く寄り添う仕事であり、図面や理論よりも「現場で感じ取る感性」「顧客の表情を読む力」「生活の温度をデザインする力」が問われる。まさにAIには代替できない“人間の手の仕事”である。
しかし日本の多くのリフォーム会社は、依然として価格競争に苦しんでいる。安さを武器にする戦い方は、自分の身を削るだけなのだが、止めることができない。
リフォームとは単なる修繕ではなく、「暮らしの再構築」である。顧客の人生に関わる仕事であり、そこにこそ職人の誇りが宿る。「日本版ブルーカラービリオネア」は難しいにしても、営業社員や職人が豊かに働ける社会を再構築することが、日本経済の内需拡大にもつながるはずだ。
さらに、近年流行した「FIRE(早期退職)」という考え方も、もはや現実的ではない。
人生100年時代においては、引退後の人生の方が長く、資産を築いても心の張りを失えば生きがいは続かない。これからの時代に必要なのは、「ノンファイヤー」――つまり引退せず、一生を通じて働き続ける生き方である。
そのためには、年齢を重ねても続けられる「誇りある仕事」「人に必要とされる仕事」が欠かせない。住宅リフォーム業こそ、その条件を満たしていると思うのだがいかがだろうか。

最高経営責任者 蜘手 健介
ロビンのリフォーム・リノベーション一覧
ロビンは、換気扇レンジフードの交換リフォームから、設計士がご提案するフルリノベーション、注文住宅まで幅広く対応しております。
それぞれのサービスの紹介、施工事例、お客様の声などをご覧ください。