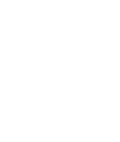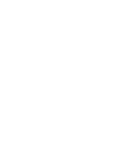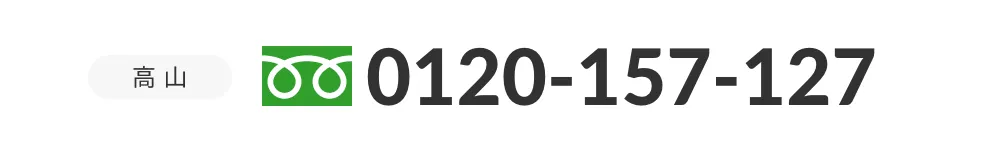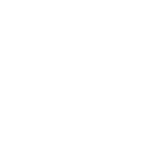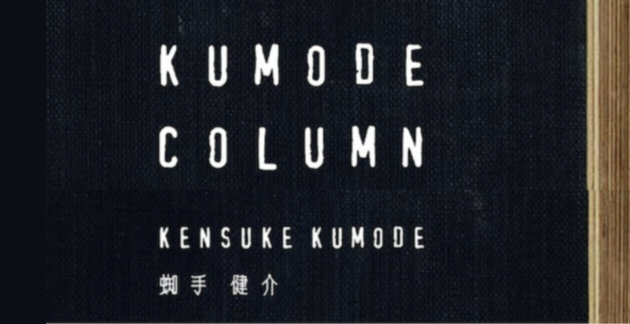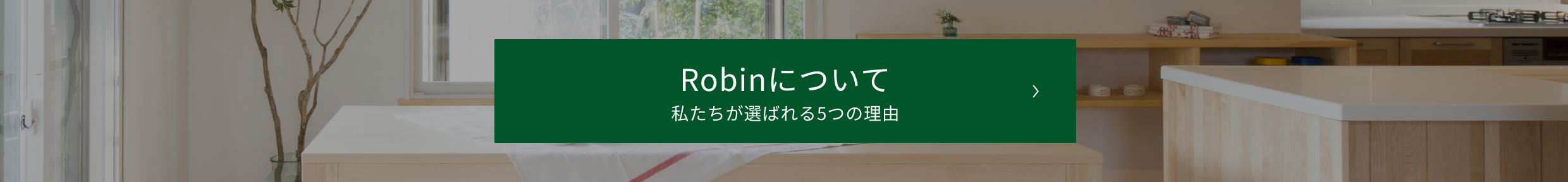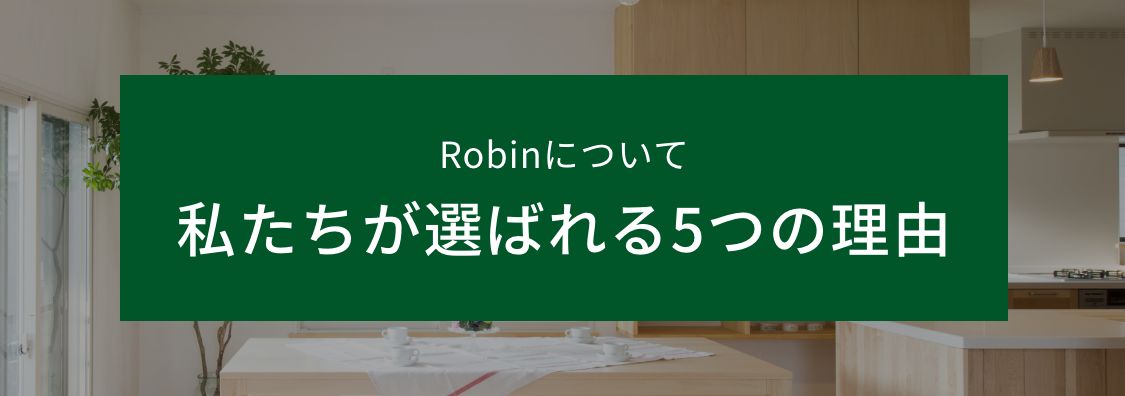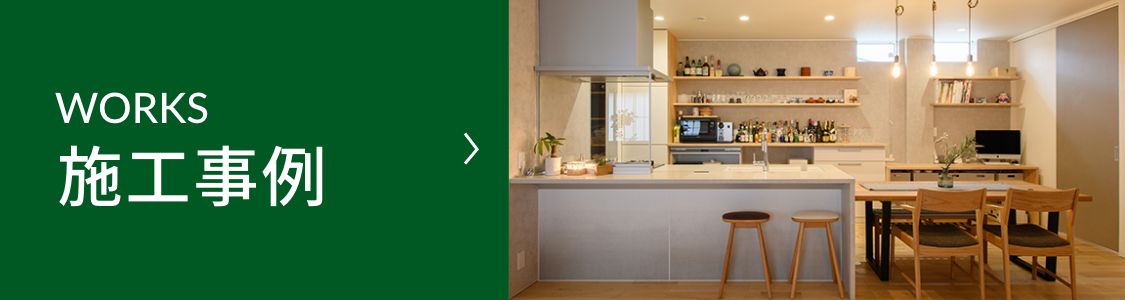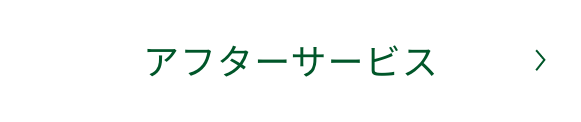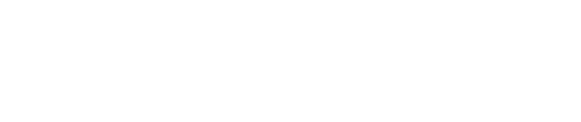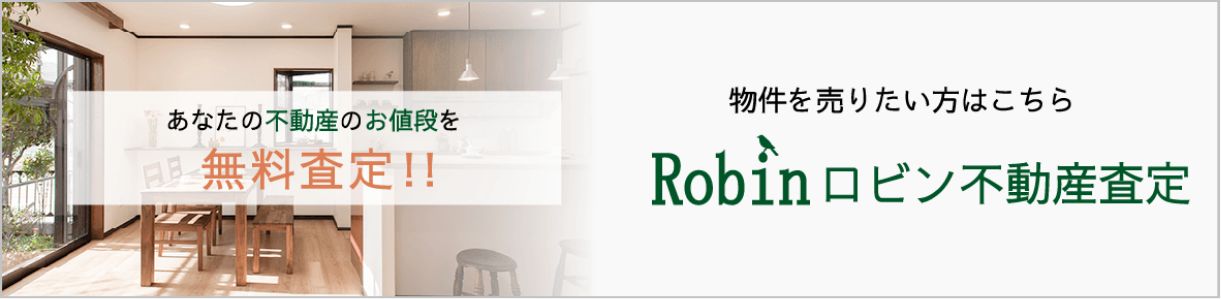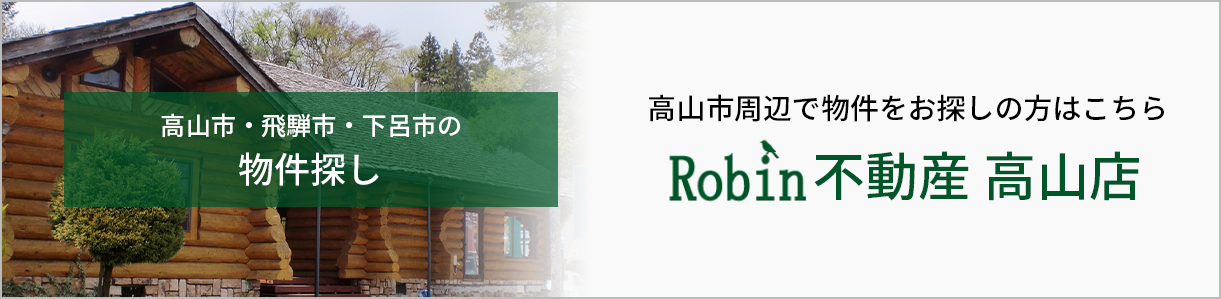(2)金は天下のまわりもの。今こそ内需経済の活性化を(2025.4.14)
世界経済はこの数十年で大きく姿を変えた。インターネットの普及、グローバルサプライチェーンの確立、資本の自由化。かつては国ごとに閉じた経済圏が、いまや互いに密接に「カップリング」し、一つの大きな経済圏として動いている。これは、確かに人類にとって大きな前進だった。モノもカネも人も情報も、国境を越えて自由に行き交い、新興国も含めて世界全体の経済規模は飛躍的に拡大した。
だが同時に、それは「足元をすくわれやすい構造」でもある。
どんなに国内で緻密で効果的な政策を打ち出しても、一国の指導者が関税を引き上げたり、戦争や疫病が発生したりすれば、瞬く間に経済の地盤が揺らぐ。たとえば、2025年現在も続くアメリカのトランプ的な通商政策は、日本企業にとって大きな打撃だ。為替が乱高下し、原材料価格が跳ね上がり、輸出入バランスが崩れる。企業業績は急変し、株価も動揺する。だが、果たしてその先にある「国民生活」は守られているのだろうか。
GDPが伸びても、株価が上がっても、それだけで「生活の質」が向上するわけではない。とりわけ日本のように、人口減少・高齢化が進行し、地方が疲弊し始めている国においては、「内需の再構築」こそが最大のテーマであるべきだ。
国民生活は、証券市場の数字や為替レートの上下にあるのではない。地域のスーパー、子どもが通う学校、親の通う病院、飲食店や美容室といった「日常」が営まれている場所にこそ、経済の本質がある。つまり、これからの日本に必要なのは、「グローバル経済」と「内需回転経済」を明確に分けて捉え、それぞれに対して別の視点で政策を設計することだ。
日本は大きな経済である世界を相手にすることも重要だが、国民生活に直結する内需経済を積極的に回すことはもっと重要である。
内需経済を回すためには、地域で人が生き、動き、働くことが前提となる。そしてその土台にあるのが「住宅」だ。人が住む場所が固定され、移動が制限されると、仕事の選択肢も限られ、消費も停滞する。反対に、住宅がライフステージや仕事、家族構成に応じて柔軟に「動かせる資産」になれば、地域間の人の流れが生まれ、サービス業や中小企業にも波及的な経済効果が期待できる。
私は住宅政策の再構築を提案したい。
今の日本では、新築住宅が資産価値を急激に失い、空き家は増え続け、住み替えには高いハードルがある。この状況を打破するために、まずは住宅の減価償却制度の導入だ。リフォームや維持修繕にかかる費用を所得控除の対象とし、「住み続ける・手入れをする」住宅の価値を税制面で評価する。
さらに、ライフサイクル型の住宅支援を整備し、子育て期から高齢期まで段階的に住み替えを支援する仕組みを作る。現在は住宅ローンという重荷に縛られ、多くの人が住み替えや移住を諦めている。たとえば、車やスマホのように残価設定型のローンを導入すれば、一定期間後に住み替え・売却・継続返済を選べる柔軟性が生まれ、若年層にも住宅取得のハードルが下がる。
家をライフスタイルに応じて変える文化の発信である。例えば仕事用の家、プライベートを過ごす家。
また、地方再生の観点からは、空き家・空き地の対策は急務だが、国家重要課題として国有化制度の導入をすべきだろう。
所有者不明・放置状態の住宅や土地を、国・自治体が強制的に取得し、公共用途やリノベーション前提の民間再販へと活用する。これは地方に仕事を生み、老朽住宅による景観や安全性のリスクも改善する。さらには、都市と地方に一つずつ拠点を持つ「2つ家」制度(Dual Home)を制度化し、空き家の有効活用と地方移住の促進を同時に図ることも可能だ。
要するに、住宅とは単なる建物ではない。人が安心して暮らし、働き、移動し、人生を紡ぐための「社会インフラ」である。だからこそ、住宅政策は単なる不動産行政ではなく、内需経済政策そのものと捉える必要がある。
グローバル経済に対応しつつ、同時に地に足のついた「分かち合いの経済」を再構築する。その第一歩は、地域の暮らしと住宅に目を向けることだ。未来の豊かさは、為替のチャートの先にあるのではない。
金は天下のまわりもの。
商店街の灯り、笑顔で集う食卓、家の灯りがついている風景。そこにこそ、本当の経済がある。

最高経営責任者 蜘手 健介
ロビンのリフォーム・リノベーション一覧
ロビンは、換気扇レンジフードの交換リフォームから、設計士がご提案するフルリノベーション、注文住宅まで幅広く対応しております。
それぞれのサービスの紹介、施工事例、お客様の声などをご覧ください。